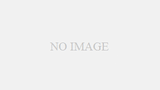こんにちは、「まなびや たぬき堂」のたぬきです。
「税金って高いなぁ…」
給与明細を見て、ため息をついたことがある人は多いかもしれません。
給料から天引きされる所得税。
何かを買えば必ずついてくる消費税。
住んでいるだけでかかる住民税や固定資産税…。
私たちの暮らしのあらゆる場面に、税金は静かに張りついています。
税金って、何のためにあるのでしょうか。
今回はそんな税金の役割について、たぬき堂らしく、やさしく、深く、一緒に考えてみたいと思います。
なぜ納税は「義務」なのか?
「税金を払うのは国民の義務です」
そう教科書に書かれていたのを、覚えている方もいるかもしれません。
でも、「義務」と言われると、少し抵抗を感じることもあるかもしれません。
ただ、「自由」な社会を成立させるには、それを支える「責任」や「仕組み」が必要です。
たとえば、誰かが病気になったとき。
「自由だから助けなくていい」という社会と、「お互いさまだから支え合おう」という社会。
本当の意味で「自由」を感じられるのは、後者のような気がしませんか?
税金は、「自分の人生を選べる社会」を支えるための、みんなの責任。
だからこそ、「義務」として位置づけられているのです。
税金の本当の役割とは?
税金の役割とは何か。
税金の役割の一つは、「みんなから集めたお金で、社会のさまざまな仕組みを支える制度」です。
でも、もう一歩踏み込んで考えてみると、税金は単なる“財源”ではありません。
実は「経済をめぐらせるための仕組み」でもあり、「社会のバランスを整えるための仕組み」でもあるのです。
お金というものは、使われることで初めて意味を持ちます。
使わずに貯め込んでいては、社会の中を循環せず、経済は停滞してしまいます。
そこで税金というシステムが機能します。
富が一部に偏って滞留してしまうのを防ぎ、必要な場所に再び“流す”ための役割を果たしているのです。
でも、実際の世の中では、お金はいつも公平にめぐるわけではありません。
「余る人」と「足りない人」。
「集まる場所」と「届かない場所」。
何もしなければ、その差はどんどん広がっていきます。
税金とは、「余っているところから、足りないところへ」お金を移す仕組み。
集まったお金は、学校や病院、インフラ整備、社会保障などを通して、私たちの暮らしに還元されていきます。
つまり、税金は「お金を止める」ものではなく、「お金を動かす」ための道具。
みんなが生きやすい社会をつくるために、お金の流れを調整する役目を担っているのです。
税金は「格差を是正」する
税金のもう一つの役割は、「格差の是正」です。
昔の日本や世界では、戦争が起こるたびに社会の格差が強制的にリセットされることがありました。
どれだけ資産を持っていても、戦争や混乱のなかで全てを失うということがあったのです。
しかし、今の日本は平和な時代が続いています。
これはとても喜ばしいことですが、一方で“自然に格差がならされる”ことがなくなりました。
その結果、お金を持っている人がますます富を増やし、持たない人はさらに困窮していくという構図が生まれやすくなっています。
「能力の差だ」「努力の結果だ」と言われることもありますが、実際には生まれた場所や育った環境による差も大きいものです。
では、格差を是正するにはどうすればいいのでしょうか?
その答えのひとつが、「税金による再分配」です。
所得の高い人が多くの税金を納め、その一部が困っている人や、将来を支える若者、子どもたちへと届く。
これは「他人に施す」行為ではなく、「社会のバランスを保つ」ための仕組みです。
税金は、社会の中で「富の一極集中」を防ぎ、やさしくならすための橋渡し。
いわば、「しあわせの分かち合い」を実現するためのルールなのです。
納税は「国のため」じゃない
これまでの話で気がついた人もいるかもしれませんが、税金は「国に取られるもの」ではありません。
税金は、社会の一員としての“参加の形”です。
誰かに命じられて払うものではなく、自分もこの社会をつくる一人なんだ、という証のようなもの。
納税は、未来への投資でもあります。
それは次の世代の教育や医療、そして安心して暮らせる社会の土台をつくること。
自分が年を重ねたとき、子どもたちが育っていくとき、その「土台」によって守られる瞬間が、きっとやってきます。
「自分のお金」が、誰かを支える
ここで大切なのは、「自分のお金が、誰かの役に立っている」という感覚です。
たとえば、あなたが納めた税金の一部が、地方の小さな保育園の運営費になっているかもしれません。
あるいは、災害時の被災者支援に使われているかもしれません。
高齢者の医療費や、障がいのある方への福祉にも。
自分とはまったく関係のない「外側の世界」に思えるかもしれませんが、実は私たちの暮らしは、見えないところでたくさんの人に支えられています。
誰かの子どもが健やかに育つこと。
誰かの親が安心して介護を受けられること。
誰かの人生が、もう一度やり直せること。
それは、まわり回って私たち自身の安心にもつながっていくのです。
税金はちゃんと使われている?
ただ、「税金って、ちゃんと使われているのかな?」
そんな疑問や不満を感じたことがある人も多いと思います。
政治家の不祥事や、意味のわからない公共事業、身内だけで回しているような予算の使い方…。
ニュースを見れば、税金の無駄遣いや不正が話題になることも少なくありません。
せっかくみんなで出し合ったお金なのに、それが自分たちの暮らしをよくするためではなく、一部の人たちのために使われていたとしたら――。
それはやっぱり、残念で、悔しいことです。
だからこそ、私たちには「関わること」が求められているのかもしれません。
選挙に行くこと。
身近な政治や社会の動きに関心を持つこと。
誰が、どんなふうに、税金を使っているのかを見つめていくこと。
それは「監視」ではなく「参加」です。
税金を出すだけではなく、使い道にも目を向ける。
私たち一人ひとりが、社会の主人公として「お金の行方」にちゃんと関わっていく。
その姿勢があってこそ、税金はもっと意味のある使われ方をしていくのだと思います。
「たくさん税金を取られるのは損」という気持ち
また最近、よく耳にするのが、「所得の高い人がたくさん税金を取られてかわいそう」「頑張って働いたのに、働き損じゃないか」という声です。
たしかに、たくさん働いて、努力して手に入れた報酬なのに、たくさん税金を引かれるのは腑に落ちない気持ちになるかもしれません。
現金給付などの制度に「所得制限」がつくと、「なんで頑張った人ばかり損をするの?」といった声もあがります。
制度をめぐって社会がギスギスしてしまうこともあります。
でも、こう考えてみてはどうでしょうか。
同じように一日8時間働いていても、高い所得を得られるということは、より多くの「社会の恩恵」を受けている、ということでもあるのです。
交通インフラ、教育制度、医療、法制度、治安の良さ…。
こうしたたくさんの「整った環境」があるからこそ、その仕事はスムーズに動き、たくさんの収入を得られるわけです。
つまり、所得が高いということは、個人の努力だけでなく、「社会からたくさんのサポートを受けている」ということでもあるのです。
だからこそ、たくさん税金を払うことは、「損をしている」のではなく、「還元している」ことなのだと捉えてみてほしいのです。
それは、社会の中で支え合うということ。
お金のあるところから、そうでないところへ。
体力がある人が重たい荷物を持つように、余裕のある人が少し多めに支える。
それは、やさしさであり、そして、つながりのしるしなのだと思います。
おわりに 税金は誰のため?それは、社会のすべての人のため
「税金は誰のため?」と聞かれたら、こう答えたいと思います。
「自分のため」であり、「誰かのため」であり、そして「社会のため」でもある。
私たちは一人で生きているようで、実は多くの人と支え合って生きています。
それを形にしてくれるのが、税金という仕組みです。
税金は、取られるものではなく、つなぐもの。
そんなふうに考えられるようになったら、税金との向き合い方も、少し変わってくるかもしれません。