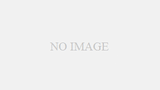こんにちは、「まなびや たぬき堂」のたぬきです。
「お金があれば何でも手に入る」
そんなふうに思ってしまうこと、ありませんか?
確かに、お金があると生活は便利になります。
家を借りることも、食べたいものを食べることも、旅行に行くこともできる。
だからつい、「お金=価値があるもの」と思ってしまうのかもしれません。
「お金のために働かなければ」「お金がないから不幸だ」「お金持ちが羨ましい」
そんな風に考えてしまいます。
どうして私たちは、お金にこれほどまでに振り回されてしまうのでしょうか。
今回は、お金の「本当の価値」について、たぬき堂らしく、やさしく、でも少し深く考えてみたいと思います。
価値を生み出すのは、人の手と知恵
実は、お金はそれ自体が価値を持っているわけではなく、「価値のあるものと交換するための道具」にすぎません。
お金の価値を支えているのは、実際にモノやサービスを生み出す“技術”や“仕事”のほうなのです。
たとえば、ある日突然あなたが1億円を手にしたとしましょう。
でも、周囲にはパン職人もいない、材料もない、道具もない。
そんな状況で、「お腹がすいたからパンを食べたい」と思っても、1億円ではどうにもなりません。
逆に、もしあなたの隣に、粉からパンをこねて焼ける職人さんがいたら?
例えその職人さんが1円も持っていなくても、あなたより先においしいパンを食べることができるかもしれません。
この話から見えてくるのは、「お金そのものには価値がない」ということです。
価値があるのは、「パンを作れる技術」や「モノを生み出す力」なのです。
パンをつくる職人がいるから、私たちはパンを買うことができます。
服をつくる人がいるから、私たちは服を着ることができます。
家を建てる人がいるから、私たちは雨風をしのいで暮らせるのです。
これらすべては、「人の手」と「知恵」から生まれたものです。
だから、本当に価値のあるのは「お金」ではなく、「価値そのものを生み出す力」だと私は思います。
私たちが何かを「手に入れられる」のは、それを作ってくれた誰かがいるからこそなのです。
お金の正体は「信用」
お金の価値は「信用」で成り立っています。
私たちが1万円札を受け取って「これで買い物ができる」と思えるのは、「このお金はちゃんと使える」と誰もが信じているから。
その背景には、「日本という国がこの紙幣の価値を保証している」という大前提があります。
でも、たとえ国が保証していても、国そのものが信用されていなければ、そのお金は使い物になりません。
実際に、経済が混乱した国では、国の通貨の価値が暴落し、人々が自国のお金を信じられなくなることがあります。
つまり、お金は「信じてもらえているから使える」だけのもの。
逆に言えば、信用がなければ、紙切れにすぎないのです。
お金とは、社会全体で共有している「信用」の象徴なのです。
お金の信用を支えるのは、モノづくり
では、その「お金の信用」は何によって支えられているのでしょうか?
その大きな要素のひとつが、「モノをつくる力」です。
日本は、世界に誇る高い技術を持っています。
自動車、機械、電子部品、アニメやゲームといった文化コンテンツまで、「日本のものを買いたい」と思ってくれる人が世界中にいます。
そうやって日本の商品や技術が世界に求められると、「それを買うために日本円が必要だ」と思う人が増えます。
すると日本円の価値が高まり、信用も強くなるのです。
良いモノをつくることが、信用をつくり、信用が通貨の価値を支えていくのです。
そしてそれは継続することがとても大事です。
これまでの日本が世界に誇る良いモノづくりをしてきたとしても、次の世代がそれを継承し、向上させていかなければ国の価値も信用も次第に落ちていきます。
一世代で国を大きくすることはできても、何世代、何百年、という年月で技術や文化を継続することはとても難しいのです。
世界中を見てみても、途中で国がなくなったり、紛争や、独裁政治で、技術が継承されなくなってしまった国がたくさんあります。
そのような中で、日本は2000年以上も国を維持し、今日まで技術や知恵を継承して来たことは世界に類を見ない素晴らしいことだと私は思います。
だからこそ、日本はこれからもモノづくりの技術を世代を超えて磨き続けていくことが大事です。
お金の信用は、国全体の「信頼の総合点」
お金の信用を支えているのは、モノづくりの技術力だけではありません。
それはもっと広く、もっと深い、社会全体の「信頼の積み重ね」によって成り立っています。
たとえば、政治が安定していること。
選挙が公正に行われ、法律が守られ、極端な混乱がない国では、未来の見通しが立てやすくなり、自然と通貨の信用も高まります。
反対に、政権が頻繁に変わったり、不正や暴力がはびこる国では、安心してその国のお金を持つことはできません。
また、社会の秩序や治安も大切な要素です。
お店に商品がきちんと並び、お金を払えば安心して物が手に入る。
こうした日常の光景は、「お金を信じられる社会」があってこそ、成り立ちます。
ルールが守られ、人々が誠実にふるまう社会だからこそ、お金のやりとりが信頼のうちに行えるのです。
そして、中央銀行の存在も見逃せません。
日本でいえば日本銀行が、物価や金利の調整を通じて、経済のバランスを保っています。
この中央銀行が政治に左右されず、冷静に判断していることも、お金の信頼性を支える重要な土台なのです。
さらに、私たち一人ひとりの行動や意識も、お金の価値を支える力になっています。
借りたお金を返す、税金を納める、偽札を使わない―そんな日々の小さな誠実さが、「この国のお金は信用できる」と思われる理由につながっているのです。
つまり、お金の価値とは、その国全体の「信頼の総合点」のようなもの。
お金は、社会のふるまいを映す鏡でもあるのです。
日本の未来は明るい
日本はこれから、少子高齢化、人口減少、資源不足など、さまざまな課題に直面します。
「昔はよかった」「少子化で景気はどんどん悪化する」「給料が上がらないから未来が見えない」と嘆く声を聞きますが、本当に必要なのは、”お金を持っていること”ではなく、”誰かのためにモノやサービスを生み出す力”です。
そこを理解したら、不安になることは何もありません。
やることはシンプルです。
”モノづくりの技術と、私たち一人ひとりの行動や意識を高めていくこと”です。
それが日本の明るい未来に繋がるのです。
日本の未来を明るく照らすのは私たち一人ひとりです。
おわりに お金は手段、豊かさは本質
お金はたしかに大切です。
でも、それを過剰に神格化したり、「お金があるから偉い」「ないからダメ」と思うのは、ちょっと違います。
大切なのは、お金の向こう側にある「人の働き」や「つくる力」に、ちゃんと目を向けることではないでしょうか。
たぬき堂ではこれからも、「本当の価値って何だろう?」という問いを、やさしく、ゆっくり、一緒に考えていきたいと思います。